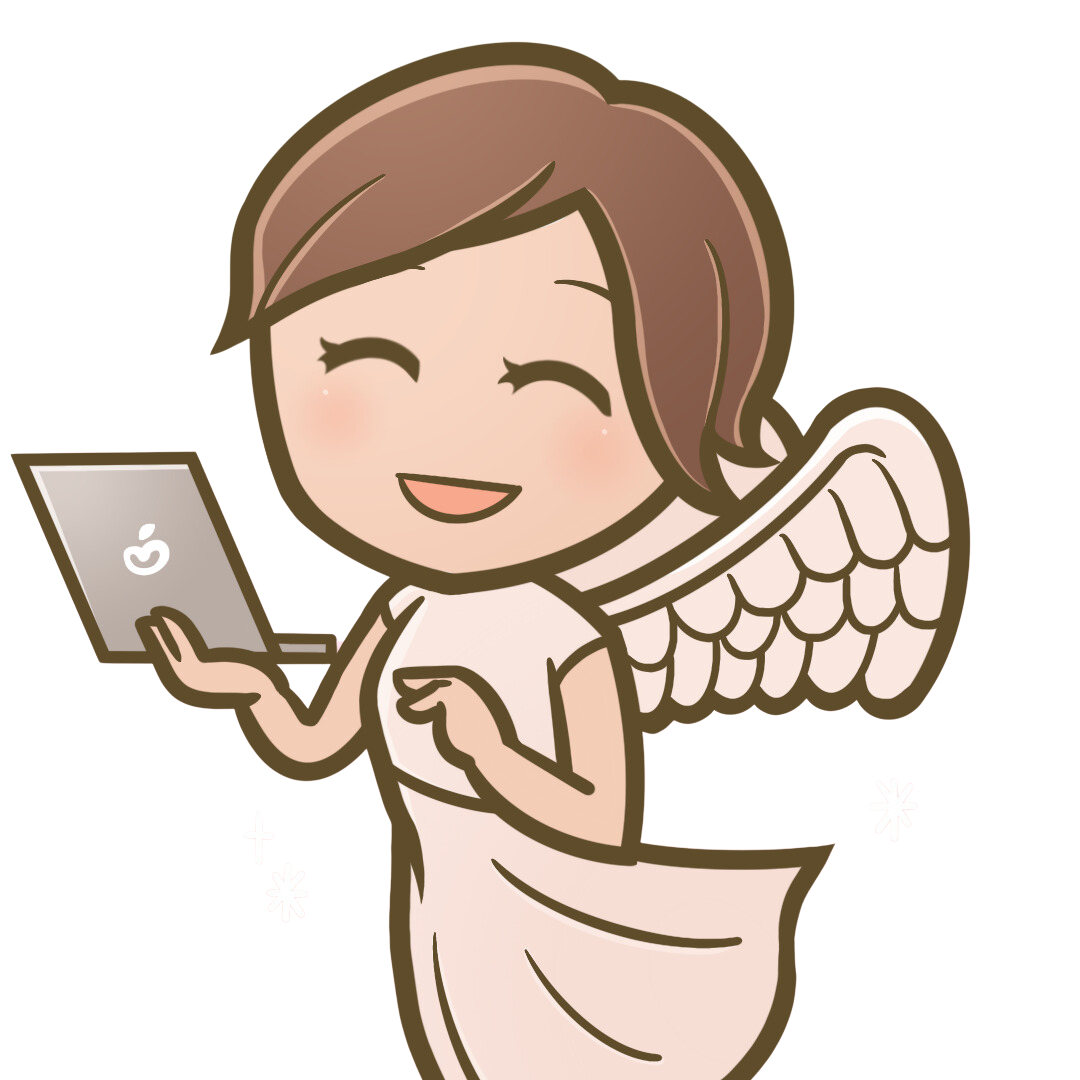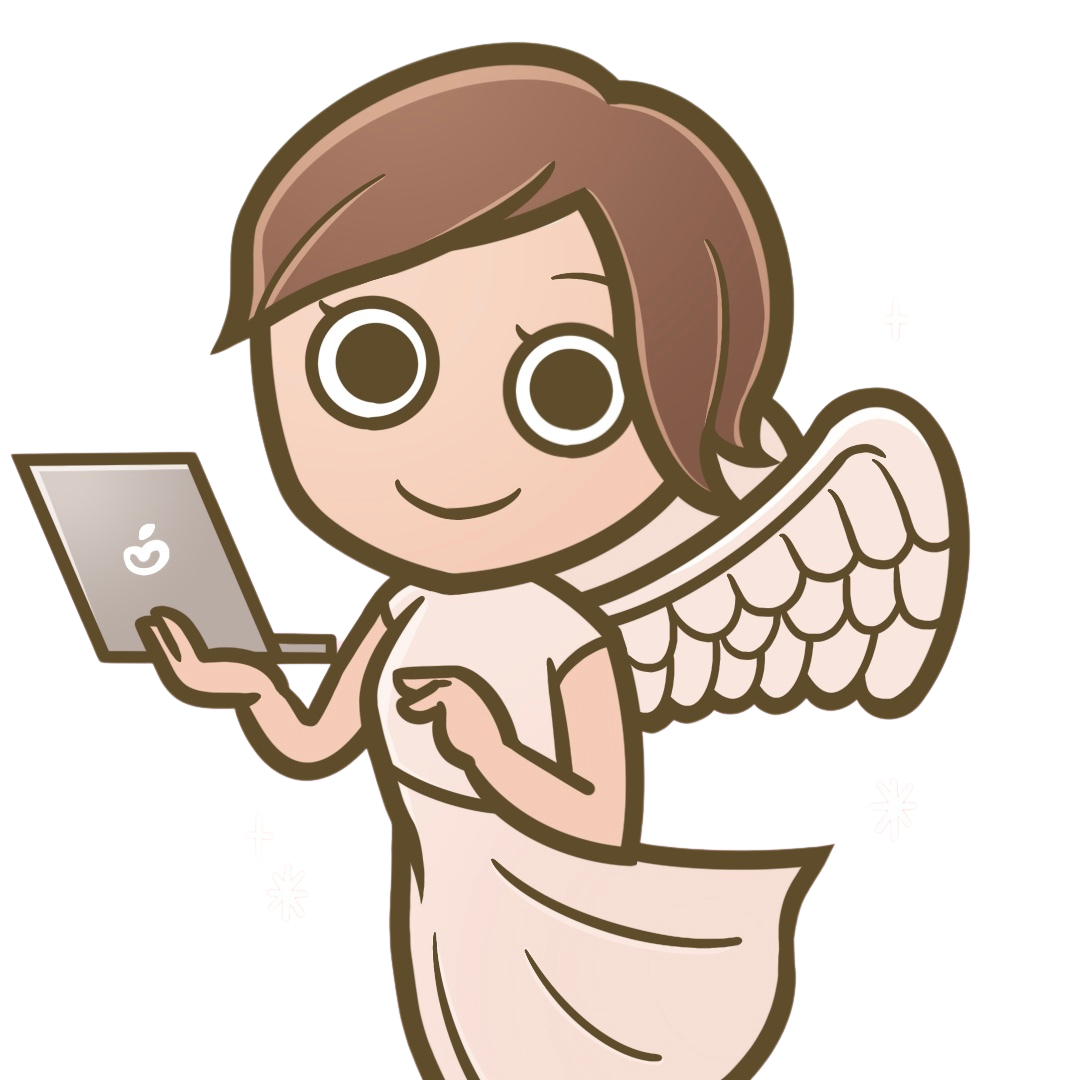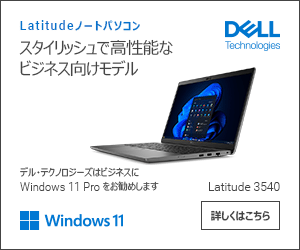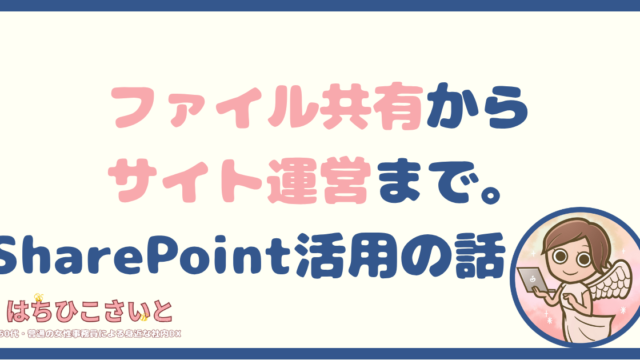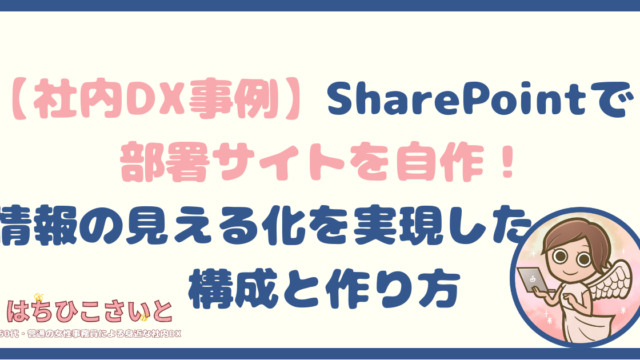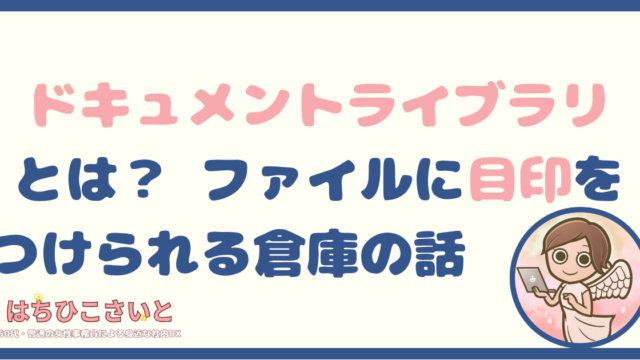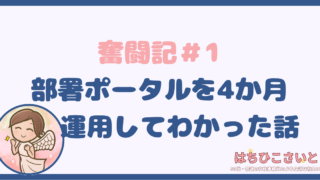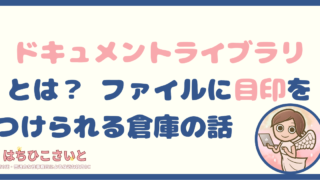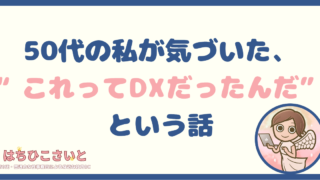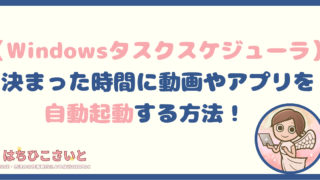部署ポータルってなに?ファイル置き場を使う場に変える話
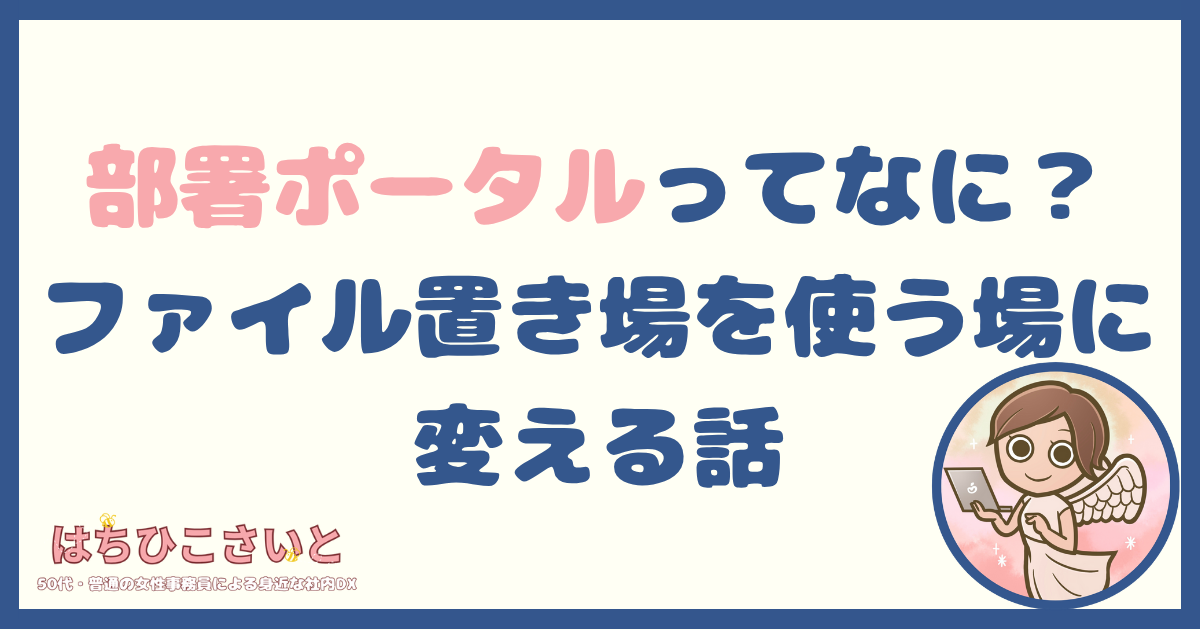
絶えず降り注ぐ情報の雨
部署ポータルを作り始めたのは、「社内の情報がとっ散らかっている」と感じたのがきっかけでした。
メールで届くお知らせ、全社ポータルに載ったという通知メール。とは言えまとまりのない情報が溢れかえった全社ポータルのUI。
末端の部署にいるからこそ、降り注ぐ情報も多種多彩。
四方八方から降り注ぐ情報の雨に感覚が麻痺して、反応する気力すら薄れていきます。
「仕事時間の3割は探し物に使っている」と聞いたことがありますが、
うちの会社はそれ以上じゃないのか……と思ってしまいます。
そこで考えたのが、コアで必要な情報を一箇所に集約する仕組み。
探す時間を減らせば、仕事の余白が増えるのではないか?
そこでとっ散らかった情報を整理するために、部署ポータルを作ることにしました。
調べていくうちに、SharePointでサイトが作れることを知り、“新しもの好き”の私の好奇心が揺さぶられました。
全社ポータルには載せられない“部署単位の情報”を、どう整理すればいいか?
とっ散らかった情報をどうまとめていけばいいか?
この記事では、私が実際に作ってみて気づいた
「部署ポータルの本当の意味」をお伝えします。
「部署ポータル」とは?
一般的に「部署ポータル」とは、部署ごとに情報をまとめて見られる場所のことを指します。
全社ポータルが“会社全体の大通り”だとすれば、部署ポータルは“部署の玄関口”ということでしょうか。
- 全社ポータル … 全社員に向けたお知らせ・ルール・方針
- 部署ポータル … 部署単位での運用・手順・締切など、実務寄りの情報
部署ごとにカスタマイズできるため、「自分たちのカラー」に合わせた設計が可能です。
SharePointなら、テンプレートを使っても、ゼロからでも簡単に作れます。
ちなみに、私の会社ではこの“部署ポータル”という仕組みが全社的に整っているわけではありません。
まだ私の部署だけが試験的に運用している段階です。
それでも、部署の情報整理がこんな風にできるのか!?と感じたことを、次の章から紹介します。
「ファイル置き場」との違い
「SharePoint=ファイル置き場」と思われがちですが、
実際に触ってみると、それ以上の使い方ができることが分かります。
- OneDriveや共有フォルダ → 単なる“保管庫”としての役割(個人・チームで保存)
- SharePoint部署サイト → 共有空間の“入口”的役割(みんなが見て使う)
部署ポータルでは、ファイルを置いたり、リンクを貼ったり、文章を書いたりデザインができます。掲示板・カレンダー・リンク集などを組み合わせて、情報の“見せ方”を整えることができるんです。
ファイル置き場は“倉庫”のようなもの。 物は整然と並んでいるだけです。
でも部署ポータルを使えば、それが“ライブ会場”や“競技場”のように変わる。 人が集まり、リアルタイムに反応し、情報が動き出すようなイメージです。
SharePointは単に「置く場所」だけではなく、「見せて・使って・響かせる場所」。
そう考えると、情報整理は工夫によってバリエーションが増えるということがわかります。

部署ポータルでできること
「サイトを作る」と聞くと難しそうですが、実際にはこんなことが簡単にできます👇
- 📰 お知らせ投稿(ニュース) 締切や重要情報を共有。画像つきで見やすく。
- 📅 締切・予定の見える化(リスト+カレンダー) 誰が見ても「今週の予定」がひと目で分かる。
- 🎥 教育・ノウハウの蓄積 マニュアル動画や記事をまとめて社内教育に。
- 🔗 リンク集・ハブ化 よく使う外部サイトや他部署の情報をまとめる。
👉 つまり、「部署のカラーを出せる“小さな情報サイト”」を、自分たちの手で作れるんです。
作ってみて感じたこと
最初は「大変そう」と思っていました。
でも実際にやってみると、“見せる箱”を作ってしまえば、そのルールに沿って情報を飾るだけ。
- デザインはドラッグ&ドロップ
- コンテンツはテンプレート形式
- 仕分けルールは条件設定
作っていくうちに、「自分たちで情報を整える感覚」が自然と身につきます。
作り手になれば、表現方法を工夫しようとして、部署の雰囲気が自然と色づいていく。
投稿した記事の閲覧数が増えたり、「見やすくなったね」と声をかけられるのも嬉しい変化でした。
部署ポータルのメリットとデメリット
実際に運用してわかった具体的な良さと課題を、あらためて整理してみます。
💡メリット
- UI設計が簡単 ドラッグ&ドロップで配置でき、デザイン感覚で構築できる。
- 誰にでも感覚的に作れる 専門知識がなくても、見たまま編集できる。
- ファイルをダウンロードせずに閲覧できる SharePoint上に保管されているので、常に最新版を参照できる。
- 視認性が高く、情報が整理されて見える 「どこに何があるか」が明確で、リンクからすぐアクセス可能。
- 部署独自の情報を発信できる コアな話題や現場の工夫を投稿できるため、部署内の結束・親近感を高められる。
- 社用スマホからアクセス可能 外出先からも確認できるため、現場スタッフとの情報共有に役立つ。
⚠️デメリット
- ⚙️ 作り手が少ない 「自分で作ろう」という人がいないと進まない。
- 🫥 存在が認知されにくい 全社ポータルですら見る人が少ない中で、部署ポータルの存在を知ってもらい、「見てもらう工夫」が必要。
- 💼 作り手の業務と認められにくい 運用や更新が“本業務外”とみなされがちで、評価につながりにくい。 それでも「誰かがやらなければ回らない」部分でもある。ここがDXの現実だと思います。
✍️ファイル置き場を“使う場”に変える仕組み
部署ポータルは、“ツールを使うスキル”よりも、 “部署の情報をどう見せたいか考える力”が問われると思います。
SharePointは、「作る人」と「使う人」がいなければ、ただの空き地。
でも一度形にすると、そこに“情報を整える文化”が根づく。
現場の言葉をDXに通訳できる人が増えたら、
きっと会社全体の情報の流れも変わっていくとはずです。
与えられた環境で工夫する。それが、現場DXのはじめの一歩です。